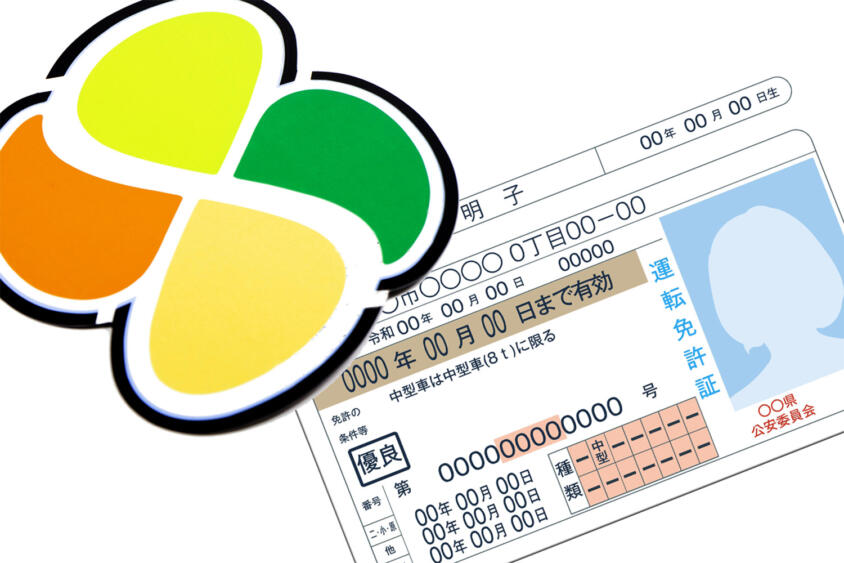
この記事をまとめると
■全国各地で高齢ドライバーによる逆走や駐車場での急発進事故などが多発している
■イギリスやニュージーランドでは70~75歳で免許更新制度が一気に厳格化される
■その他にも海外では運転地域の限定や夜間運転の禁止など運転を制限する場合も多い
高齢者ドライバーの免許問題に対する海外での施策
2010年代に入って、日本では高齢ドライバーに関する報道が増えた印象がある。なかでも2019年4月に東京・池袋周辺で発生した高齢ドライバー運転による歩行者の死亡事故は、「池袋暴走」と呼ばれ大きな話題となった。
そのほかにも、全国各地で高齢ドライバーによる逆走や駐車場での急発進事故などが多発したことを重く見た国(警察庁)は、高齢ドライバーが運転免許を更新する際の仕組みを抜本的に変えた。具体的には70歳以上では高齢者講習の受講を、また75歳以上では認知機能検査を義務付けた。
また、運転に自信がない高齢者、または家族からの説得されて運転を止めようと思った高齢者などは、運転免許の自主返納(いわゆる免許返納)という選択をするようになってきた。ただし、全国的にみると免許返納の割合は池袋暴走の前後では上昇したものの、その後は緩やかに上昇、または一時的に減少した地域もある。
こうした高齢ドライバーに関する運転免許事情は概ね、海外でも同じような傾向がある。年齢では、肉体的な衰えを感じる人が多い70歳や75歳という人生の節目で、運転免許更新に一定の制限を設ける場合が少なくない。
たとえば英国の場合、70歳未満では運転免許の有効期限が10年だが、70歳以上では3年へと一気に短縮され、さらに健康状態を報告する必要がある。また、ニュージーランドでは運転免許有効期限は75歳未満では10年だが、75歳になった時点で更新する必要があり、場合によっては医師の診断書の提出や実技試験を行う。
年齢をベースとした制度と並行して「限定免許」という考え方を導入しているケースもある。代表的な事例は、オーストラリアのニューサウス・ウェールズ州だ。日常生活における移動区域を限定するもの。買い物、病院、役場、さらには勤務先や友人宅など具体的に移動する場所やルートについて運転免許を発効する地元機関と高齢ドライバー、またはその家族などと協議して決める。
そのほか、アメリカの一部では限定免許の条件として、夜間の運転を禁止、高速道路走行の禁止、また同乗者のいる場合のみといった内容を加味する。
クルマが生活の足であり、かつ公共交通機関がない、または不便な土地柄であれば、地域社会全体として高齢者の移動を考える一助になっているといえる。
日本でもこうした高齢ドライバーの限定免許に関する研究や、地方自治体や国での協議が行われているものの実施に向けた具体的な動きには至っていない。
