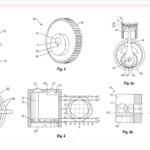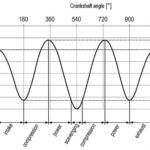熱効率を上げe-fuelを用いて内燃機関の復権を図るか
では、その真意は、ということだが、どうやらシリンダー下部に、シリンダーの円周に沿って複数の吸気ポートが設けられ、ピストントップが円周上のポート位置より下がることで、この吸気ポートから空気の導入が行えるようになるようなのだ。といっても、大気圧だけでは空気の導入は不可能だ。そこで威力を発揮するのが過給機ということになる。過給機で圧縮された空気がポートからシリンダー内に圧送されるかたちで充填される。
ここからは推測だが、ピストン上昇過程のある段階までシリンダーヘッドの排気バルブが開き、燃焼ガスを排出。加圧されてシリンダー下部のポートから導入された空気が、シリンダー下方から燃焼ガスを押し出す効果を見越した方式ではないかと思われる。燃焼ガスをシリンダー内に再導入して燃やす考え方はEGRと同じ、といったら乱暴だろうか? しかし、熱効率は確実に引き上げられる。
 EGRバルブのイメージ画像はこちら
EGRバルブのイメージ画像はこちら
これも推測だが、ポルシェ6ストロークエンジンの狙いは、熱効率の引き上げにあるのではないか。簡単にいってしまえば、燃やした燃料からどれだけエネルギーとして活用できるかが熱効率で、熱効率が高いほどクルマを走らせるのに必要な燃料量は少なくなる。つまり、消費燃料が少なくなれば、排出する二酸化炭素の量を抑えられる、ということになるからだ。
さて、考えるべきはここからで、これまでどおり化石燃料を使うのであれば、いかに熱効率に優れた6ストロークエンジンとはいえ、二酸化炭素の排出は避けられない。つまり、時代に逆行するのが内燃機関ということになる。この二酸化炭素の排出を低減ではなくゼロにするため、電気モーターによるEVの普及が急がれているわけだが、2023年3月、世界に先駆けドイツ国会で、将来的にe-fuel(合成燃料)を使う内燃機関車の製造・販売が認められるようになった。これは、内燃機関にとっての一発大逆転だった。
 e-fuelのイメージ画像はこちら
e-fuelのイメージ画像はこちら
e-fuelは、炭素と水素によって燃料を作り出す方法で、炭素は大気中の二酸化炭素を原材料とする。炭素を大気中から取り入れ、燃焼によって再び大気中に放出するため、大気中の二酸化炭素の量は増えもせず減りもせず。いわゆるカーボンニュートラルとなり、地球環境の破壊にはつながらない、という考え方だ。
こうした場合、e-fuelを使う内燃機関車は、二酸化炭素排出の点でEVと同じ条件に立てることになる。ポルシェは、e-fuelによる内燃機関車が社会的に認められた状況下で主導権を握る立場を目指し、新たに内燃機関の特許を出願、取得したと思われる。気になるのは実際の性能で、登場に期待が寄せられる新エンジンである。
振り返れば、フェルディナント・ポルシェの作った1号車は電気自動車(EV)だった。100年以上も前に無公害車を作っていたポルシェが、今度は内燃機関車で無公害車の先頭に躍り出たことになる。モーターレーシングの世界、高性能スポーツカーの世界で名を馳せるポルシェだが、社会と密接な関係にあるモータリゼーションの立場でも、第一級の自動車メーカーであることを思い知らせる特許の取得劇だった。