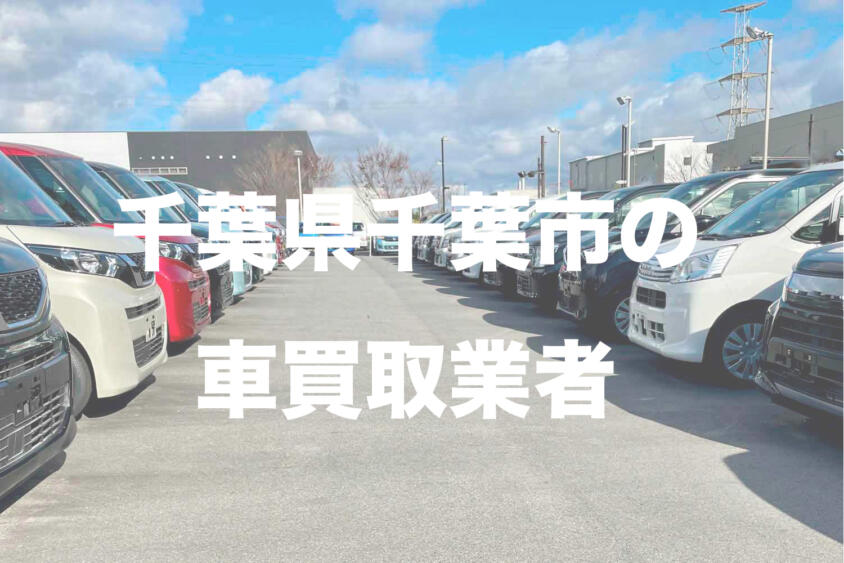この記事をまとめると
■グリーンスローモビリティとは、低速のEVを利用した公共交通サービス
■地域が抱える交通の課題の解決や、低炭素型交通の確立が期待されている
■東京都杉並区が運用しているグリーンスローモビリティに乗ってみた
グリーンスローモビリティの魅力を体感!
最近、耳にする機会が増えた「グリーンスローモビリティ」。国土交通省や環境省からは「時速20km未満で公道を走ることができる、電動車を活用した小さな移動サービス」と定義づけられた。導入推進の背景には、21世紀後半に温室効果ガス排出実質ゼロの国際的枠組みを目指した、「パリ協定(2015年)」があるといわれている。
「グリーンスローモビリティ」の特徴は、
Green:CO2排出量が少ない電気自動車
Slow:低速走行をするために、乗客が周囲をゆっくりと見物できるから観光に適している
Safety:速度が速くないので安全あり、高齢者も安心して運転できる
Small:小型なので狭隘路走行が可能
Open:窓がないため開放感がある
とされ、
・高齢者の移動手段の確保
・観光客を対象とした利便性の高い周遊手段
を目的とした展開が想定されている。これまで、国土交通省や環境省が支援事業として推進し、各地で実証実験が行われてきた。すでに、本格運用の段階に入ったところも多数ある。
 グリーンスローモビリティ画像はこちら
グリーンスローモビリティ画像はこちら
そのなかのひとつに、東京都杉並区が2024年11月から定期運行をしている路線がある。JR中央線(東京メトロ丸の内線)荻窪駅西口から南方面に、約2.5㎞の周回コース(東まわり一方向のみ)だ。停留所は、起終点の荻窪駅西口を合わせて4カ所(大田黒公園、荻外荘公園、桃井第二小学校)である。
杉並区は東京23区西部にあり、区議会をもち議員や区長が選挙で選ばれる「特別区」だ。人口は約60万人(2020年)で、中核市に匹敵する規模をもつ。大正末期以降に住宅地として発展したこともあり、旧くから住む人の多いベッドタウンだ。そのために高齢化が進んでいる一方で、東京中心部(オフィス街)に近いこともあり、20歳代、30歳代の人口比率が高いという特徴を合わせもつ。
 グリーンスローモビリティの車内画像はこちら
グリーンスローモビリティの車内画像はこちら
こういった事情から、杉並区は「誰もが気軽で快適に移動できる地域社会の実現」を目指して、本システムの導入に踏み切ったわけだ。本路線の地域は、決して有名観光地が多いわけではない。しかし、音楽評論家大田黒元雄の自邸を整備した太田黒公園や、近衛文麿の邸宅であった荻外荘を公園として整備した荻外荘公園があり、インバウンドが興味をもちそうな施設も点在する。
地域住民の移動手段と観光客の足という二面性をもつ本路線は、7人乗りのバス型車両と5人乗りのカート型車両(いずれも乗客定員)で、毎日(荒天時を除く)9時から16時半までの間に、24便が運行されている。事業主体は杉並区で、運行事業者はタクシー事業などを営むキャピタルモータースである。
 グリーンスローモビリティの車内画像はこちら
グリーンスローモビリティの車内画像はこちら
荻窪西口を出てしばらくは片道1車線のバス通りで、そこから住宅街を抜けながら狭隘路に入っていく。エアサスの利いた路線バスに乗り慣れていると、少々ダイナミックな乗り心地だ。しかし、住宅街、歩行者、自転車などの生活感がある風景と、同じ目線で移動する経験はほかでは味わえない感覚である。最高時速20km/h未満は決して早い速度ではないが、狭隘路では無理のない走行なので安心感がもてる。
1周しても25分、途中下車すればさらに短い乗車時間だが、ほかの乗り物では得られない体験や利便性を考慮すれば、運賃100円(1乗車、未就学児は無料)にはお得感があるといえる。観光客からすれば街なかを歩くような感覚だから、疲れているときや荷物が多いときなどには重宝するであろうし、高齢者にとってはエレベーターのようなインフラとして、利用できるのではないだろうか。
 グリーンスローモビリティの乗降口画像はこちら
グリーンスローモビリティの乗降口画像はこちら
現状では事業として成立させるのが難しいかもしれないが、車両、運行形態、ルート、営業形態など多方面から改良を重ねることで、収支の好転を十分期待できよう。「グリーンスローモビリティ」は、近い将来に自動運転技術などと併せて、鉄道、バス、自動車と並ぶ移動交通手段に成長するのではないだろうか。