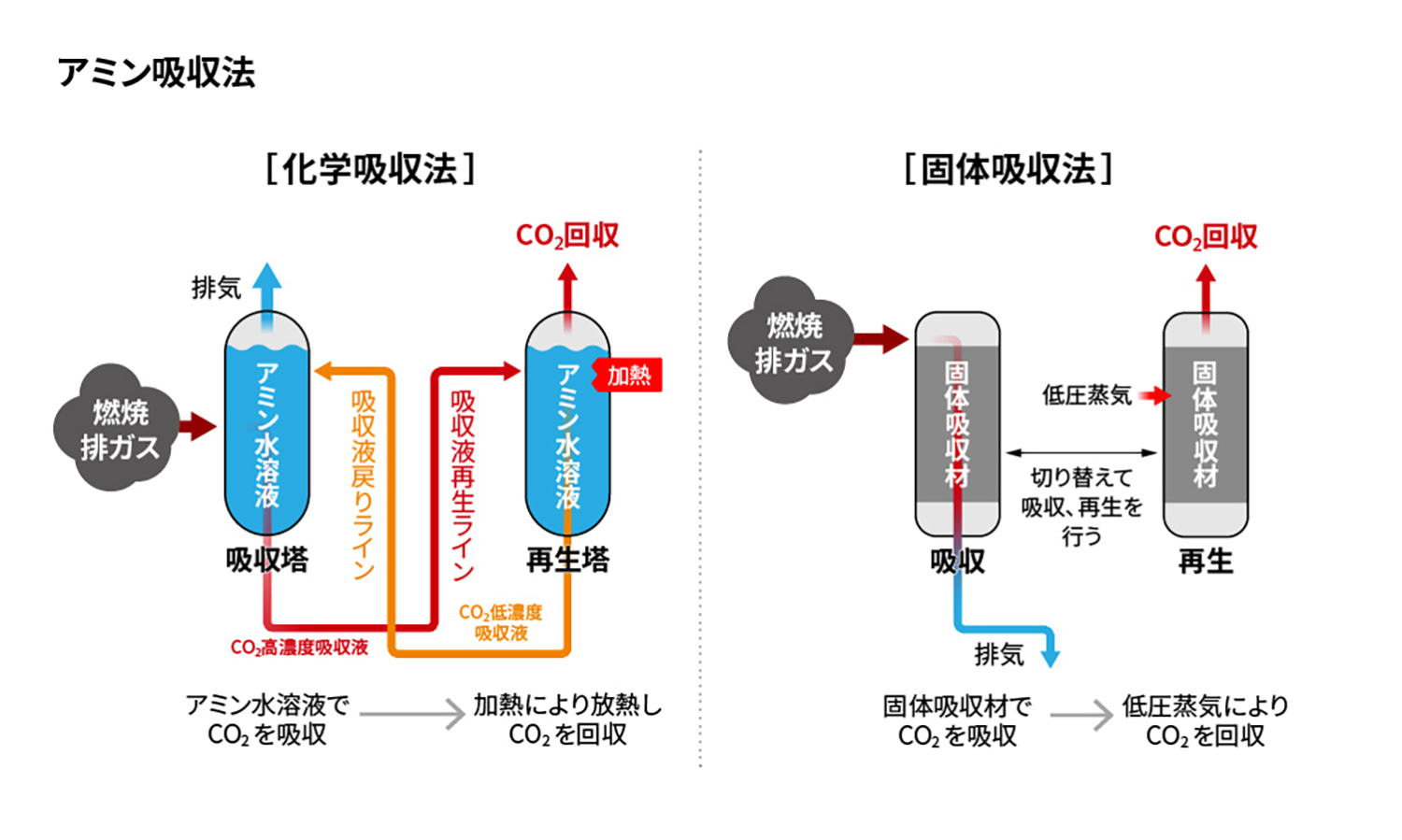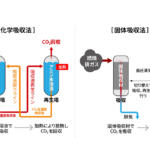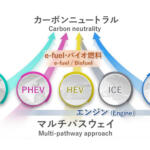出すそばから二酸化炭素を回収できればエンジン車でもよくない? いま自動車メーカーが取り組む「CO2キャプチャー」とは (2/2ページ)
編集部が選ぶ!
あなたにおすすめの記事
-
トヨタ・スバル・マツダが「エンジン」の重要性を語る! クルマ好きなら知っておくべき「マルチパスウェイ」の中身

-
「カーボンニュートラル」=「エンジンの廃止」ではない! トラック業界から考える「燃料生成」の手段

-
【PR】【2026年最新】おすすめ車買取一括査定サイトランキング|メリット・デメリットも解説

-
EVが嫌いなんじゃない! 純エンジン車が好きなだけなんだ! 押し寄せるEV化の波のなかで死ぬまで「エンジン車」に乗り続ける方法を考えてみた

-
新興国もBEVだけが解決の道じゃないと気がついた! BEV減速の裏にある「マルチパスウェイ」の効果

-
「エンジン屋」のホンダまで2040年にエンジン搭載車をゼロに! 「内燃機関ファン」阿鼻叫喚の現実

自動車コラムニスト

- 愛車
- スズキ・エブリイバン(DA17V・4型)/ホンダCBR1000RR-R FIREBLADE SP(SC82)
- 趣味
- モトブログを作ること
- 好きな有名人
- 菅麻貴子(作詞家)