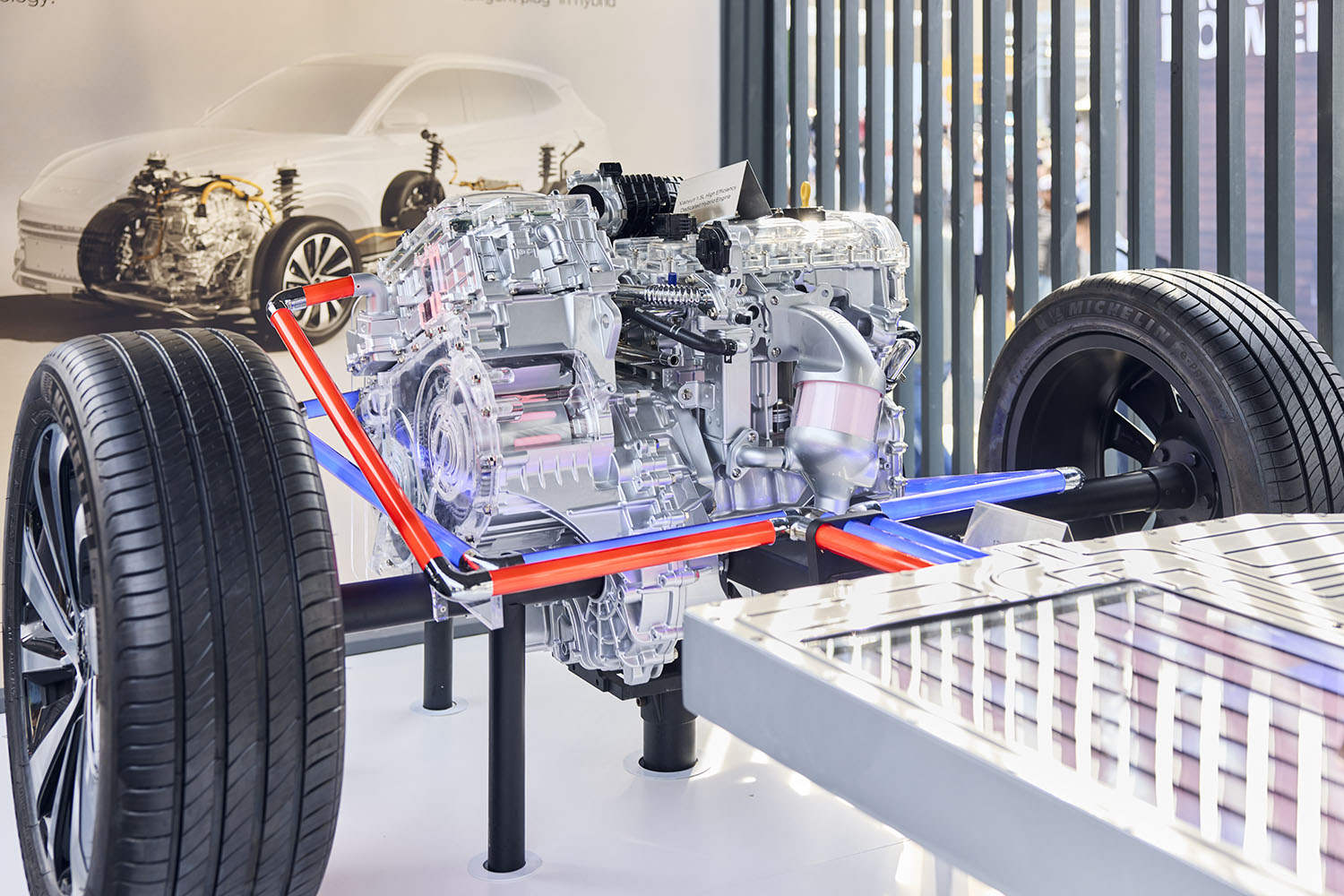ドイツで開催される「IAAモビリティ2025」で「BEVが脇役」化! 世界中で刻々と変わりゆく電気自動車の立ち位置 (2/2ページ)
編集部が選ぶ!
あなたにおすすめの記事
-
BEVはいいクルマがあれば売れる……とはいかない! 「4年縛りルール」「販売員のBEV知識取得」と売るためのハードルはかなり高かった

-
【PR】【2026年最新】おすすめ車買取一括査定サイトランキング|メリット・デメリットも解説

-
各国のEVの普及に立ちはだかる「バカ高い保険料」! EVが「これから」の日本はどうする?
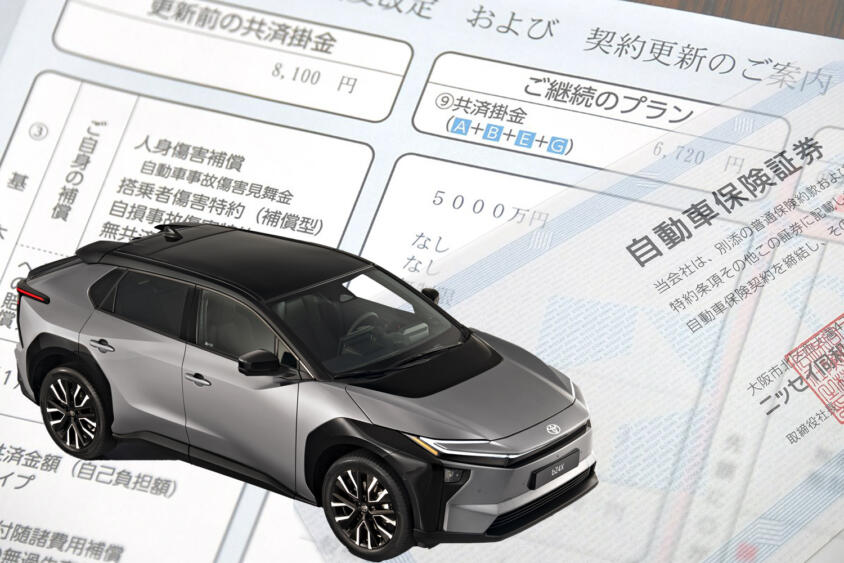
-
中国車が話題にのぼりがちなアジアのモーターショーで日本車の勢いが凄い! インドネシアでみた「やっぱり日本車」感

-
世界で進む商用車のEV化! 日本メーカーのラインアップが増えないと輸入車に市場をもっていかれる可能性!!

-
トランプ大統領の次なる標的は「CHAdeMO」! 日本独自のEV充電規格はアリかナシか?

小林敦志 ATSUSHI KOBAYASHI
-

- 愛車
- 2019年式トヨタ・カローラ セダン S
- 趣味
- 乗りバス(路線バスに乗って小旅行すること)
- 好きな有名人
- 渡 哲也(団長)、石原裕次郎(課長) ※故人となりますがいまも大ファンです(西部警察の聖地巡りもひとりで楽しんでおります)