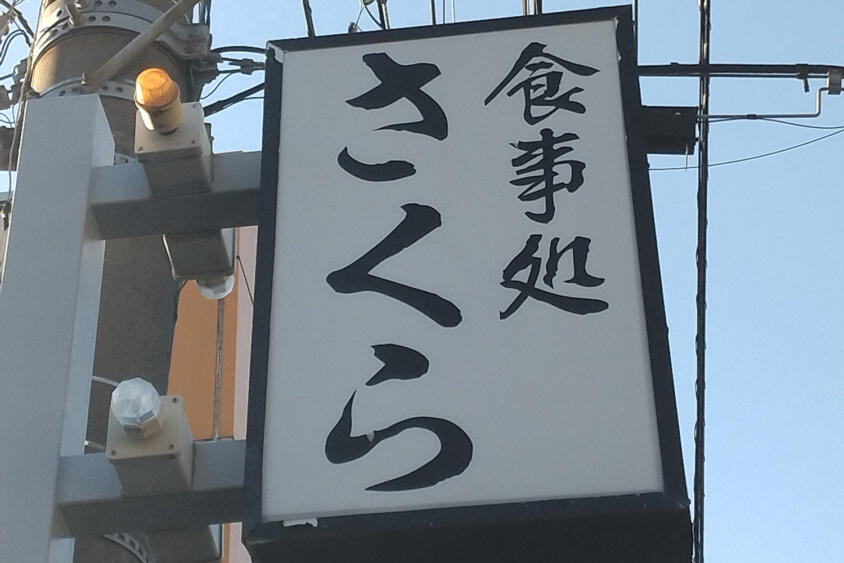この記事をまとめると
■工事や点検の際などに行われる高速道路の車線規制
■規制を知らせる灯火類やパイロンなどが設置される
■規制帯は誰がどのようにつくっているのか解説
規制帯づくりは命がけの作業
高速道路は速く走ることができて信号もないから、じつにスムースかつ快適な移動を楽しむことができる。とくに長距離移動では、なくてはならない便利な存在だといっても過言ではないだろう。しかし、多くの車両が高速で通行する以上、道路の劣化や損傷などを避けることはできず、それに伴う工事、点検作業は不可欠なのである。
高速道路上で点検、メンテナンス工事、緊急工事などをするときには、全面通行止めになることもあるが、複数ある車線を一部規制する場合も多い。高速道路は制限速度が抑えられている区間もあるが、多くは80km/hや100km/hで走行が可能だ。近年では、110km/hや120km/hまで制限速度が伸びている区間もある。このようななかで、規制帯をつくるのはまさに命がけの作業といえよう。
 規制帯のイメージ画像はこちら
規制帯のイメージ画像はこちら
なので、最近は規制帯を設置するにあたって、安全かつ便利な車両が開発されてきている。しかし、これらはすべての区間に配置されているわけではない。むしろ、現在でも手作業による規制帯づくりの方が多いとさえいわれているのだ。100km/hで通過する車両を横目に、事故なく安全に規制帯を作るのには、いったいどのような手順を踏むのであろうか。
じつは、工事などの規制が行われる付近の制限速度は概ね50km/hに制限される。これが守られていれば、作業の安全性はある程度高まるのだが、実際はなかなかそういうわけにはいかないのが現実だ。結局、作業員は100km/h程度の速度で走る車両の横で、規制帯を作らなければならないのである。