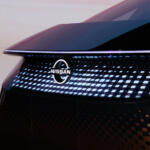日産の「追浜ではクルマを作らない」に悲観の声続々! ただし追浜から完全撤退ではないってどういうこと? (2/2ページ)
編集部が選ぶ!
あなたにおすすめの記事
-
日産の顔とも言える追浜工場におけるクルマの製造終了を決定! 日産の未来を守るために苦渋の決断を下した理由

-
2026年度までに黒字化できなかったら辞めるってマジか! 背水の陣で日産再建に臨む「エスピノーサCEO」ってどんな人物?

-
「これが自動車工場?」圧倒されるハイテクの館! 日産「インテリジェントファクトリー」が凄かった

-
「GT-RやZは作らねばならない!」 窮地の日産が「改めて日本は重要な市場」と表明して今後の新車投入や戦略を説明

-
「純利益93.5%減」=「販売台数が大幅減」ではない……が9000人のリストラ! ホンダとの統合も検討されるいま日産に何が起こっているのか?

-
【PR】【2025年最新】おすすめ車買取一括査定サイトランキング|メリット・デメリットも解説

自動車コラムニスト

- 愛車
- スズキ・エブリイバン(DA17V・4型)/ホンダCBR1000RR-R FIREBLADE SP(SC82)
- 趣味
- モトブログを作ること
- 好きな有名人
- 菅麻貴子(作詞家)