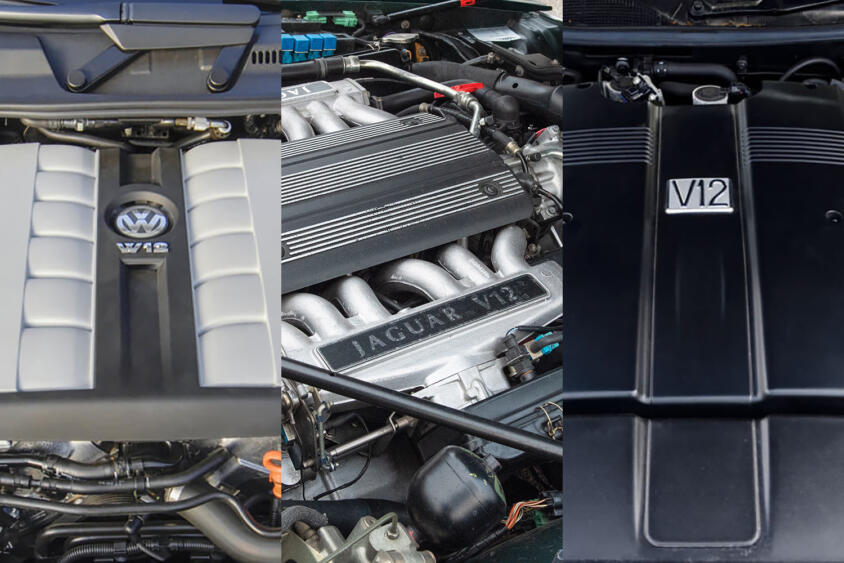クルマに採用するメリットよりデメリットのほうが目立つ
しかしながら、ボディサイズと気筒数の関係でみると、2輪車とクルマでは状況が大きく異なります。2輪車では4気筒エンジンは大排気量のハイパフォーマンス系モデルとなりがちですが、4輪車では4気筒はエンジン横置きのFF車、つまり大衆車がメインとなっていました。
 ホンダ・フィットのエンジン画像はこちら
ホンダ・フィットのエンジン画像はこちら
大衆車の車両パッケージを考えると、エンジンスペースをできるだけ小さくして、そのぶんキャビンを広げるのが正解となります。エンジン横置きを前提にすると、V4エンジンは前後スペースを広く必要としますから、それだけキャビンが狭くなるわけで、大衆車向きではないのです。
また、2輪車においてV4エンジンは、エンジン幅をタイトにできる形式です。多くの2輪車がそうであるように、クランクシャフトが横向きとなるように積んだとき、前から見ると直列2気筒相当のエンジン幅になるのがV4エンジンのメリットです。しかし、全幅1.7m前後がスタンダードな乗用車においては、直列4気筒だからといって前面投影面積が広がってしまうことは、ほとんど考えられません。
 日産マーチ(K13)画像はこちら
日産マーチ(K13)画像はこちら
2輪車のサイズではエンジンという重量物がハンドリングに与える影響は大きく、マスの集中化というのは運動性能に直結するメリットですが、少なくともエンジン横置きのFF車では、エンジン重量の集中化が、大きなメリットにつながるとは考えづらいのも事実。むしろ、整備性の悪さというデメリットのほうが、ユーザーからは嫌われるでしょう。
また、1970年代以降どんどん排ガス規制が厳しくなってきています。排気系がふたつにわかれるV型エンジンは、排ガス処理装置のコストが上がります。大排気量が商品力につながるプレミアムモデルならまだしも、大衆車においてコストアップ要因につながるV4エンジンを採用する必然性はないというのも、4輪車からV4エンジンが消滅した理由といえそうです。
 ランチア・フルヴィアのV4エンジン画像はこちら
ランチア・フルヴィアのV4エンジン画像はこちら
さらにいえば、クルマの場合は、形式を変えてエンジンをコンパクトにするのではなく、レス・シリンダー志向、すなわち気筒数を減らしてエンジンを小さくすることが、近年のトレンドです。直列4気筒をV4エンジンにして小さくするのではなく、直列3気筒エンジンにするというアプローチがメインストリームになっています。
ターボチャージャーによる過給やモーターと組み合わせるハイブリッド化を前提に進められるという4輪車ならではの状況も、レス・シリンダーの推進力になっているといえ、このあたりは自然吸気エンジンが主流の2輪車との大きな違いです。
 ホンダS660のエンジン画像はこちら
ホンダS660のエンジン画像はこちら
レス・シリンダーというトレンドにおいて、大衆車のエンジンが4気筒から3気筒にシフトしていることを考えると、ミッドシップに多気筒エンジンを積むようなスーパーカーのエンジンが4気筒化することも十分に考えられます。その際、あえてコスト高の傾向にあるV4エンジンに置き換えることで、スーパーカー的なプレミアム性を維持するというアプローチで、4輪車にV4エンジンが復活するかもしれません。
独特の重低音を響かせるV4エンジン搭載のスポーツカーに、あなたは乗ってみたいですか?