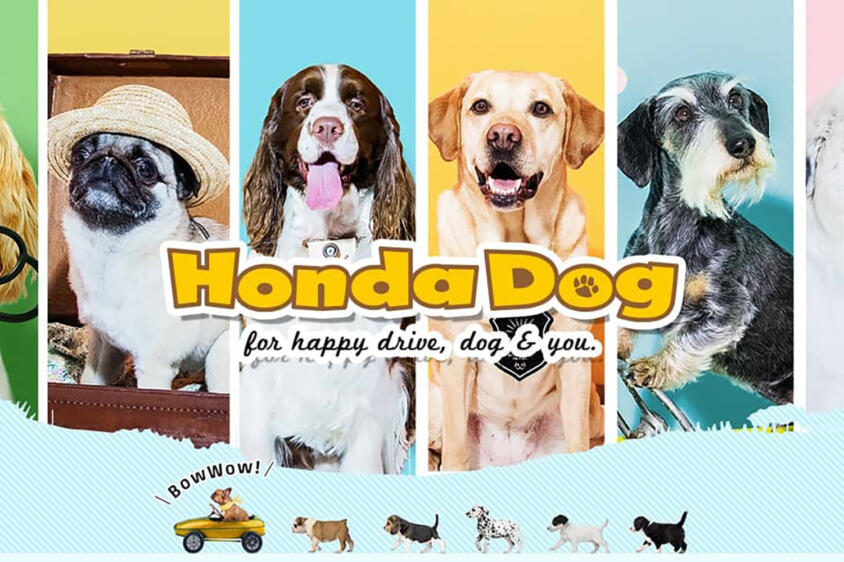このままでは宅配が貴族の使うサービスに
そして今後起こるであろう物流の2030年問題は、日本の人口に占める高齢者の割合が2030年におよそ30%になるのに加え、少子化により人口そのものが減少し、就労可能人口の減少がさらに顕著になると予想されていることがその根拠になっている。その影響により先述したとおり、同年には国内の34.1%の荷物が運べなくなると試算されているのだ。つまり2030年問題は物流のみならず、日本の産業全体に降りかかる深刻な危機になる問題をはらんでいるわけだ。
とくにトラック業界は、現在でもドライバーのおおよそ半数(49.7%)が50代以上であり、将来を担う重要な世代である若手・30代以下ば24.9%しかいない。しかも60代以上のドライバーは19.4%以上。この世代は必然的に近い将来現役を引退し、さらなる人手不足を招くことになる。
 トラックドライバーのイメージ画像はこちら
トラックドライバーのイメージ画像はこちら
政府をはじめ行政やトラック業界もこれに対し手をこまねいているわけではない。前述の「トラック新法」の施行はその代表的な施策で、トラック運送の適正運賃の授受や、荷待ち・荷役時間短縮の義務化による物流生産性向上、ドライバーの賃上げなど業界改善のためのあらゆる対策が条文化し、今後進められていく。
またデジタル技術の活用による物流DXの推進や自動運転フォークリフトなどによる荷役の効率化。モーダルシフトの推進や自動物流道路の計画、ダブル連結トラックの稼働開始や自動運転トラックの実用化など、ソフト面・ハード面双方による対策が今後行われていくといわれている。
 自動運転フォークリフトのイメージ画像はこちら
自動運転フォークリフトのイメージ画像はこちら
政府は、これらの対策により今後運ばれなくなるであろうと予測されている、国内輸送貨物の34.1%を補う34.6%相当の貨物輸送効果を生み出そうと試算しているが、その実現は非常に困難であると業界内では見られている。
自動運転トラックの実用化は、それに向けてさまざまな社会実験が行なわれていることは日々報道されて入るが、今はまだ限られた大手運送会社と自動運転ソリューションベンダーによる実験が行われているのみで、もう5年後になる2030年に完全な実用化が間に合うかどうかは疑問だ。
 自動運転トラックのテストイメージ画像はこちら
自動運転トラックのテストイメージ画像はこちら
また荷主だけでなく、わたしたち消費者も物流に対する意識を見直さなければいけないところまで来ている。EC・通販にともなう宅配はその最たるもので、ポイント還元実験による再配達削減や「送料無料」表示の見直し、置き配の標準化が進められているが、これまでのように送料無料や再配達がさも当たり前であるかのような意識は捨て去らなければならない。
そうしなければ、2030年以降はこの宅配も、一部の富裕層だけが利用できる高価な商材になってしまうことも十分ありうるのだ。