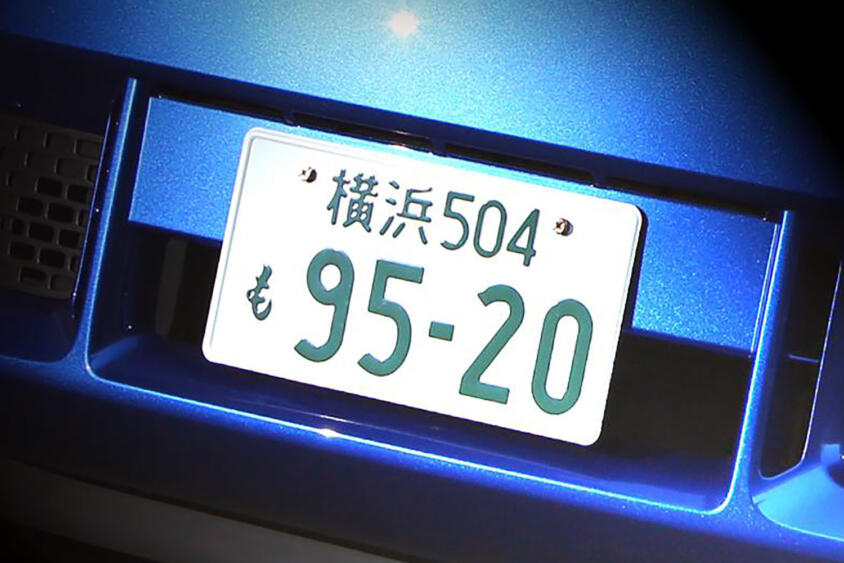寄付金は地域の活性化に使われている
この際に納められた寄付金は、その地域の交通改善、観光振興などの取り組みに活用されることになっています。つまり、ご当地ナンバープレートを取得することは、自分が住む地域や勤務する地域の魅力を発信する役割を担うことになり、寄付金をプラスして収めれば、具体的な取り組みに間接的に参加できることになるのです。
では、具体的な活動とはどんなものがあるのかというと、多くの地域が寄付金の活用方針を議論し、公表しています。たとえば宮城県の仙台では、東北各地の観光スポットをクルマで巡るドライブスタンプラリーイベントの企画や、自然景観や地元グルメを紹介し、クルマで自由に周遊するロードトリップの推進など、ドライブ観光事業への活用を想定。
 伊達政宗の銅像画像はこちら
伊達政宗の銅像画像はこちら
さらに、具体的な活用方針を公表しているのは茨城県のつくばナンバーで、バス停留所へのベンチ等の設置、カーブミラーやガードレールの設置、踏み間違い防止装置やドライブレコーダー等安全装備の設置補助、子育て世帯向けの自動車関係グッズ(子どもの乗車を示すマグネットやチャイルドシート等)の配布、購入補助となっています。
多くの地域がこうした交通安全や地域活性化イベント、暮らしを助けるために寄付金を使用することを公表しており、カラフルなご当地ナンバーが増えればそれだけ実現するものも多くなるということですね。
 つくば市のバス停画像はこちら
つくば市のバス停画像はこちら
ただし、2024年12月末時点でのご当地ナンバープレートの普及率は、決して芳しいものではないようです。地域ごとのデータになりますが、普及率のトップ3は3位が青森県の弘前で5.02%。2位は島根県の出雲で5.56%。そしてダントツの1位が奈良県の飛鳥で8.53%。そのほかはいまだ1%に満たない地域もあり、活用計画に必要な寄付金に達していないために、活用開始を見送っている地域も見られる状況です。
 飛鳥ナンバーのイメージ画像はこちら
飛鳥ナンバーのイメージ画像はこちら
ご当地ナンバープレートはなんとなく「特別感がほしいから」とか「目立ちたいから」などという理由で取得しているのかと思っていた人もいるかと思いますが、寄付金をプラスして取得することで地域の暮らしや魅力向上のために貢献できるということなんですね。そうと知ると、カラフルなご当地ナンバーを付けているクルマが地域の救世主に思えてくるかもしれません。
もし、これから新たなナンバープレートを取得する機会があれば、カラフルなご当地ナンバープレートの取得を検討してみてはいかがでしょうか。