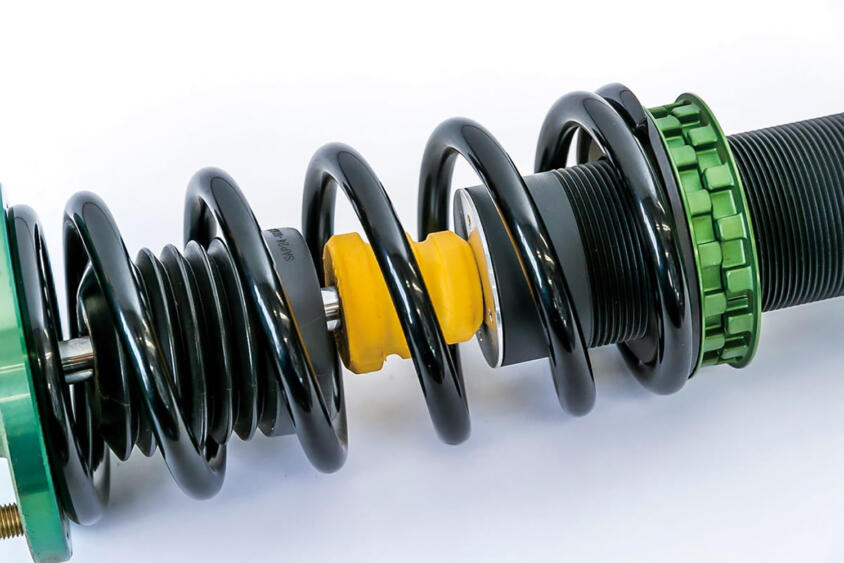この記事をまとめると
■デコトラ文化は1970年代に誕生し『トラック野郎』で全国に広まった
■デコトラ=派手な装飾という認識は大きな間違い
■令和のデコトラは荷室となるボディに手を加えるのがトレンド
『トラック野郎』が火をつけた昭和のデコトラブーム
1970年代に誕生し、現代まで続く日本が誇るデコトラ文化。その正確な起源は明らかではないが、鮮魚を運んでいた東北地方のトラックが飾りを取り付けたのが始まりではないかといわれている。
そして、1975年から1979年にかけて公開された映画『トラック野郎』の大ヒットをきっかけに、この「トラックを飾る文化」は日本全国へと広まった。その結果、デコトラは自動車好きによる改造車という枠を超え、広く一般にも知られる存在となったのである
昭和のデコトラはとにかく派手に飾ることが目標とされていた。龍や虎などの絵を描き、数多くのランプを取り付けて仕事の相棒であるトラックを飾り立てたのである。
「派手じゃなきゃデコトラじゃない」の誤解と令和のスタイル
こうしたスタイルは平成中期ごろまで続いたが、次第に派手なトラックは荷主や取引先から歓迎されなくなっていった。周囲の目を気にする風潮が強まり、改造車であるデコトラは厳しい扱いを受けるようになってしまったのである。その結果、現代ではド派手なデコトラを目にする機会は、かつてに比べてずいぶん少なくなったといわれている。
そのためか、SNSなどでは「デコトラがいなくなった」と知った顔で話す人が増えているが、じつのところはそうではない。むしろデコトラの数そのものは、全盛期と呼ばれた昭和の時代よりも間違いなく増えているのである。
 バンパーを取り付けたトラック画像はこちら
バンパーを取り付けたトラック画像はこちら
なぜ知識のない人たちはデコトラがいなくなったと感じるのだろうか。その答えは単純明快で、いつまでもデコトラ=派手だという時代遅れな認識でいるからである。
「派手じゃなければデコトラではないだろう」という声が聞こえてくるようであるが、当初から「派手だからデコトラだ」という取り決めやセオリーなどは存在しなかった。それはあくまで先入観にすぎず、昭和の時代からシックに決めたデコトラは数多く存在したのだ。それに、現代では仕事クルマではなくプライベートで派手なデコトラを楽しむ愛好家が、全国各地に存在している。
どの世界でもそうだが、時代に合わせた進化を遂げていくことこそが、文化を長続きさせるための秘訣である。デコトラはまさにそのような形で、現在でも変わらず生き続けているのだ。もちろんサイドパネルやリヤドアに絵を描いたようなド派手な仕事クルマを見る機会は減った。しかし、それは決して「デコトラが消えた」ということを意味しない。
 積荷を下ろしているトラック画像はこちら
積荷を下ろしているトラック画像はこちら
近年のデコトラ界では飾りではなく荷室となるボディに手間暇をかける傾向が強いのだが、それは素人目には何がすごいのかわからないレベル。荷主を刺激しないよう配慮した装飾こそが、令和時代の新たなトレンドとなっている。日本が誇るデコトラ文化はそれほどまでに奥が深く、偉大な世界なのである。
世のなかを生き抜くためにはアップデートしていくことが重要となる。それができない文化は自ずと衰退していくもの。そう考えると、デコトラという文化はまだまだ続いていくに違いない。