この記事をまとめると
■2000年代前半までは車両価格の20%超といった新車の大幅値引きも珍しくなかった
■奨励金減額と原価上昇によって販売会社としてもメーカーとしても利益は減少している
■残価設定ローン普及が値引き期待を下げたこともあり大幅割引は消滅した
かつてモデルライフのタイミング次第では大幅値引きが期待できた
2000年代の前半までは、値引きは全般的にいまよりも多額だった。各モデルで発売直後は値引きを引き締めたが、1年以上を経過すると拡大傾向を強め、マイナーチェンジを実施する2年後の値引き額は車両価格の10%を超えてくることが多かった。車両価格が200万円であれば、値引き額は20万円以上で、300万円なら30万円に達する。
その後も、値引き額は時間の経過に伴ってさらに拡大する。フルモデルチェンジを控えたころの決算期には、値引き額が車両価格の20%前後に達する車種も少なくなかった。車両価格が300万円なら、60万円以上の大幅値引きもあった。
ところがいまは、販売店によると「人気車でも不人気車でも、そこまでの値引きはムリ」という。理由を尋ねると「メーカーから支給される販売奨励金が大幅に減り、クルマの価格は高まったが、1台当たりの利益は増えていないから」と返答された。
 商談のイメージ画像はこちら
商談のイメージ画像はこちら
2008年のリーマンショックのころまでは、決算期を中心にメーカーは販売会社に販売奨励金を支給していた。販売店では、これを原資として値引き額の上限を引き上げ、大幅値引きも行われていた。
ところが近年は、全般的に販売奨励金を支給する機会が減ったり、金額を減額している。そうなると大幅値引きも難しい。
また販売店の指摘どおり、クルマは値上げされても利益は増えていない。車両販売に伴う利益は、簡単にいえば「車両価格 − メーカーの卸値」だ。メーカーの卸値が高まった割に小売価格は上昇していないため、販売会社の車両販売による利益も減っている。
ちなみに、メーカーの開発者も「メーカーの利益は減っている」という。つまり販売会社、メーカーともに1台あたりの利益を抑えているわけだ。メーカーでは「昨今の安全装備の充実などに基づくコストアップと、原材料費や輸送費の高騰は想像以上だ。これらをすべて価格に転嫁したら、大幅な値上げになってしまう。これでも値上げは最小限度で行っている」と説明した。
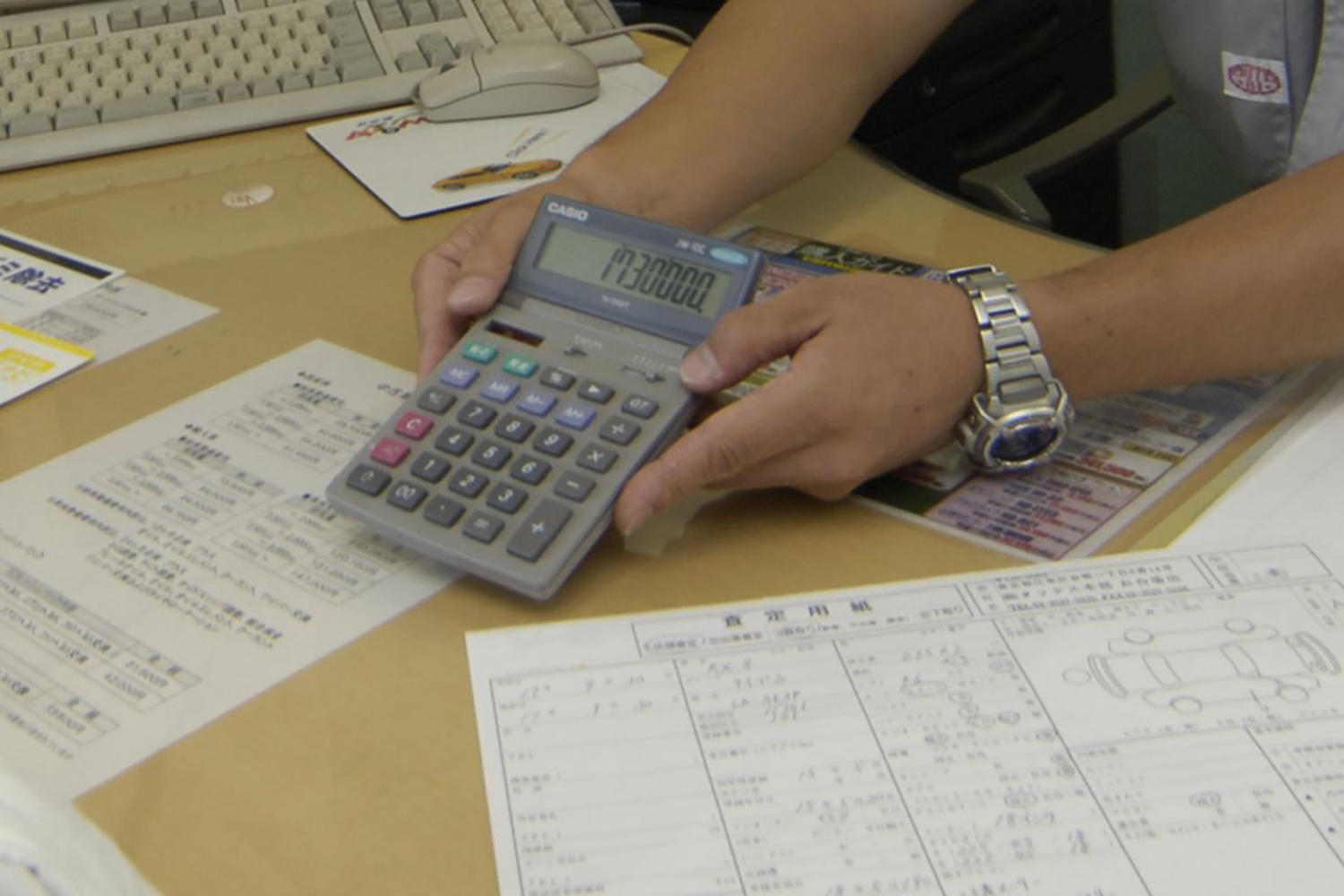 値引きのイメージ画像はこちら
値引きのイメージ画像はこちら
そのほか残価設定ローンの普及も、値引き額が減った理由に挙げられる。返済期間満了時の残価を除いた金額を返済する残価設定ローンを使うと、値引きを少し増やしても、月々の返済額に与える影響は小さい。いい換えれば残価設定ローンには、ユーザーの値引きに対する関心を下げる効果があるわけだ。
これらの事情に基づいて、昨今は値引きが大幅に減っている。

