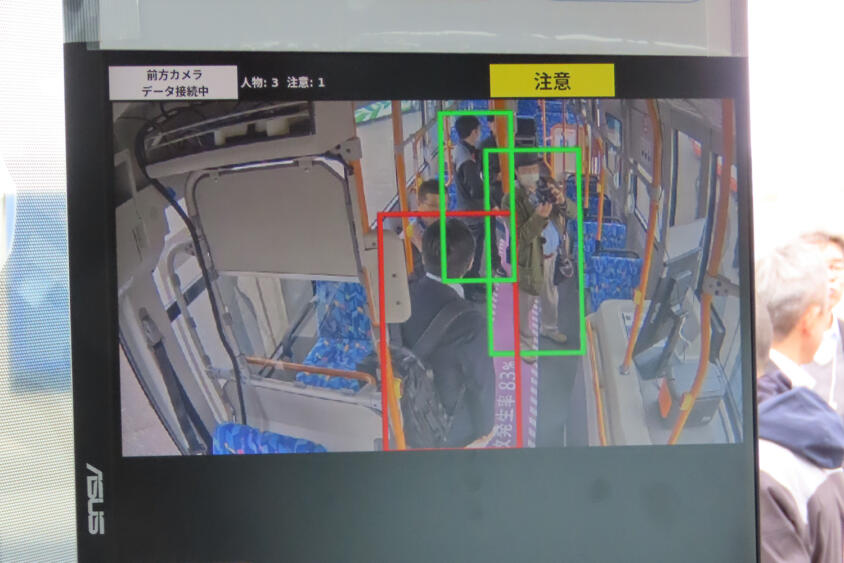日本ではもっとライドシェアを一般化する必要がある
日本のライドシェアは、稼働日や稼働時間が厳しく管理・限定されている。なので、歩合給をメインとした給与体系では、限られた時間でガツガツ稼ごうとする気もちにもなり、それが事故や乗客とのトラブルなどを誘発しやすくなる。タクシーの世界でも「家族のために」などと、とにかく稼ぎたいと真面目に乗務する運転士のほうが、事故や乗客からのクレームが目立ったりすることも多いのである。ややゆったりと構えた運転士のほうが稼ぎもよく、事故やクレームも少ないとされることも多い。
 タクシーヘビーユーザーが考える日本でライドシェアを広めるために必要なこと画像はこちら
タクシーヘビーユーザーが考える日本でライドシェアを広めるために必要なこと画像はこちら
日本全国、どの業種でも慢性的な働き手不足が続いている。しかし、大学生を筆頭とした若者のアルバイト先というのは、意外に限られてしまうようで、若年層であっても、アルバイトのような副業や仕事が探しにくくなっているようなのである。1度提出したら、原則そのシフトに沿って仕事をするような、シフト制をとっている飲食店やコンビニなどのアルバイトであれば、まだまだ探せば求人はあるが、スケジュールに融通が利きにくいことから、近年の人気は低めだという。
 コンビニバイトのイメージ画像はこちら
コンビニバイトのイメージ画像はこちら
その点、日本のライドシェアは、前述したように地域によって稼働日や稼働日数が決まっているので、当然就業日や就業時間も固定されるし、必ず毎回従事する必要もない。飲食店などのように、決まったシフトとして仕事が入ることはないのである。
ただし、ライドシェアドライバーの求人はあまり多くはない。地域によっては不要論も出るほど、タクシーの稼働実績が戻ってきており、タクシーの稼働不足を補完するという役割自体が薄れてきているのが、その背景にある。
 タクシーのイメージ画像はこちら
タクシーのイメージ画像はこちら
しかし、諸外国のライドシェアに比べれば、東南アジアなど新興国あたりでは、副業ではなく正業として就いているようなドライバーも目立つ。そんな背景もあるのか、みんなガツガツしているようで、マッチングを試みてもキャンセルされることも多い(電話番号などで外国人とわかると面倒くさいとなるらしい)。
日本のライドシェアは、実質タクシー会社が囲い込んでいるので、いまの状況をよろしくないと思う人もいるようだが、運営するタクシー会社としては、将来のタクシー運転士のリクルートも兼ねて運営しているところも多いようなので、タクシー業界の雇用対策のひとつ、そして若年層の雇用環境整備などの観点で、さらにブラッシュアップできないものかとも考えているそうだ。
 ライドシェアのイメージ画像はこちら
ライドシェアのイメージ画像はこちら
一方で、無人タクシーの営業運行が世界各国ではじまっている。しかし、現状では営業区域が限定されるなか、無人タクシーによる交通違反対策など、新たな問題も出てきている。なお、人が運転するタクシーのように自宅前まで迎えにはきてくれないという。
技術的な面よりも監督官庁によるさまざまな規制が、無人タクシーの前には立ち塞がっているようにも見え、すべてのタクシーが無人運行するという時代はまだ少し先のことのように見える。
 海外で運用される無人タクシーのイメージ画像はこちら
海外で運用される無人タクシーのイメージ画像はこちら
南カリフォルニアではどこでもライドシェアがマッチングすると2分ほどで迎えにきてくれていた。長距離ではなく、短距離移動で細かく稼ぐことを好む傾向もあるので、地元の人でマイカーのない人が、近くの商業施設への買い物に行くのにも利用している光景も珍しくない(日本でもお年寄りが近所のスーパーへ買い物に行くのにタクシーを利用するケースが目立ってきている)。
欧米など諸外国のライドシェアサービスそのものを真似せずとも、「日本でももう少し当たり前のようにライドシェアが普及していたら便利なのに(とくに筆者の住む郊外地域では)」と感じている。