この記事をまとめると
■かつてエンジンは高回転まで回れば回るほど高性能とされていた
■今の環境重視な世の中には不釣り合いなため貴重な存在だ
■なかでも9000回転以上のタコメーターをもつ超高回転エンジン車を紹介する
エンジン屋の作るクルマはやっぱり高回転至上主義だった
環境志向かつ電動化が進む現在では想像できないかもしれないが、かつてエンジンは「いかに高回転まで許容できるのか」というのが評価されていた。
そんな時代の評価軸を示す言葉が、ホンダS660のホームページに書かれている。そこには、次のような文言が並んでいるのだ。
 S660走り画像はこちら
S660走り画像はこちら
「回すよろこび」にあふれる高回転化
「何回転からレッドゾーンなのか」
「エンジンを高回転まで回してシフトアップする喜び」
「スポーツカーのエンジンは、高回転まで回るほうがエラい!」
とはいえ、S660の3気筒ターボエンジンのレッドゾーンは7700rpmからという設定で、回してなんぼという時代のスポーツカーのエンジンに比べると、全然高回転エンジンには感じられないというのも、オールドファンの実感だろう。
 S660タコメーター画像はこちら
S660タコメーター画像はこちら
とくに小排気量エンジンであれば、回転でパワーを稼ぐのが常套手段だった。なにしろパワー(最高出力=仕事率)というのは、エンジン回転数とトルクをかけて導かれるスペックといえる。つまり、高回転まで回すことはハイパワーに直結するのだ。
そんな高回転エンジンを積んだ国産モデルの代表といえるのがS660の直系のご先祖様、ホンダ「S600」だろう。1964年に生まれた総排気量606cの4気筒DOHCエンジンは、最高出力57馬力を8500rpmで発生するという超高回転ユニット。
 S600全体画像はこちら
S600全体画像はこちら
さらに、1万1000rpmまで表示されたタコメーターのレッドゾーンは9500rpmからとなっていた。キャブレター仕様なのでレブリミットという制御はなく、どこまでも回っていく精密機械と呼ばれた名機だ。
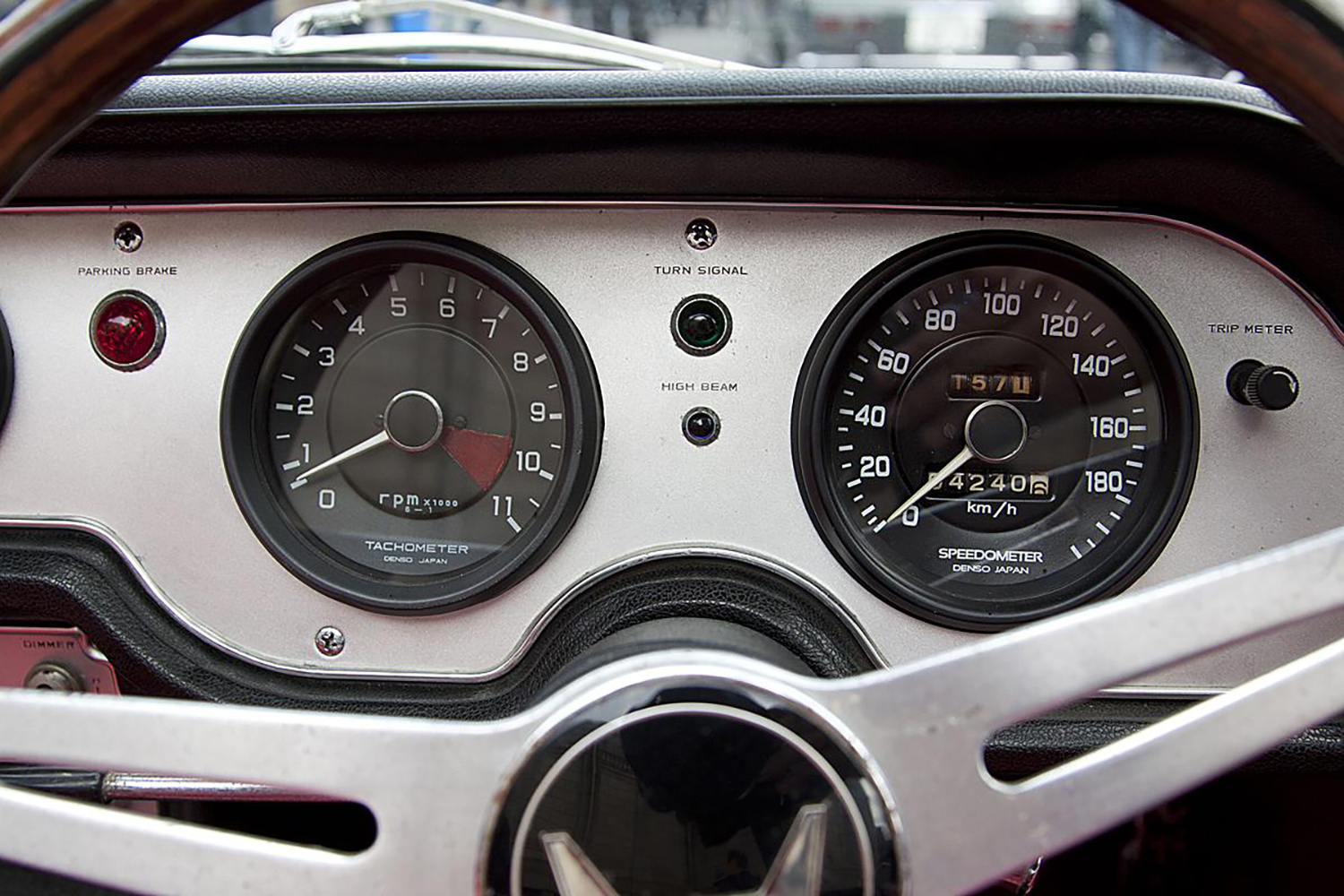 S600タコメーター画像はこちら
S600タコメーター画像はこちら
そして、排気量を示す数字の前に「S」を置くホンダスポーツは高回転エンジンがアイコンだったともいえる。ホンダ50周年を記念して生まれたFRスポーツカー「S2000」においても、レブリミットは9000rpmだったのである。
 S2000全体画像はこちら
S2000全体画像はこちら
より正確にいえば、S2000のなかでも2リッターエンジンを積む前期型(AP1)のレブリミットが9000rpmだった。実際、バータイプのタコメーターはほぼ1万rpmまで刻まれ、9000rpmからがレッドゾーンとなっていたのには、多くのドライバーが気圧されたものだ。
 S2000メーター画像はこちら
S2000メーター画像はこちら
心臓部である「F20C」エンジンは、最高出力250馬力を8300rpmで発生し、最大トルク22.2kg-mの発生は7500rpmというスペック。単に9000rpmまで回るというわけではなく、高回転まで回すことでパワーもトルクも絞り出す仕様となっていた。
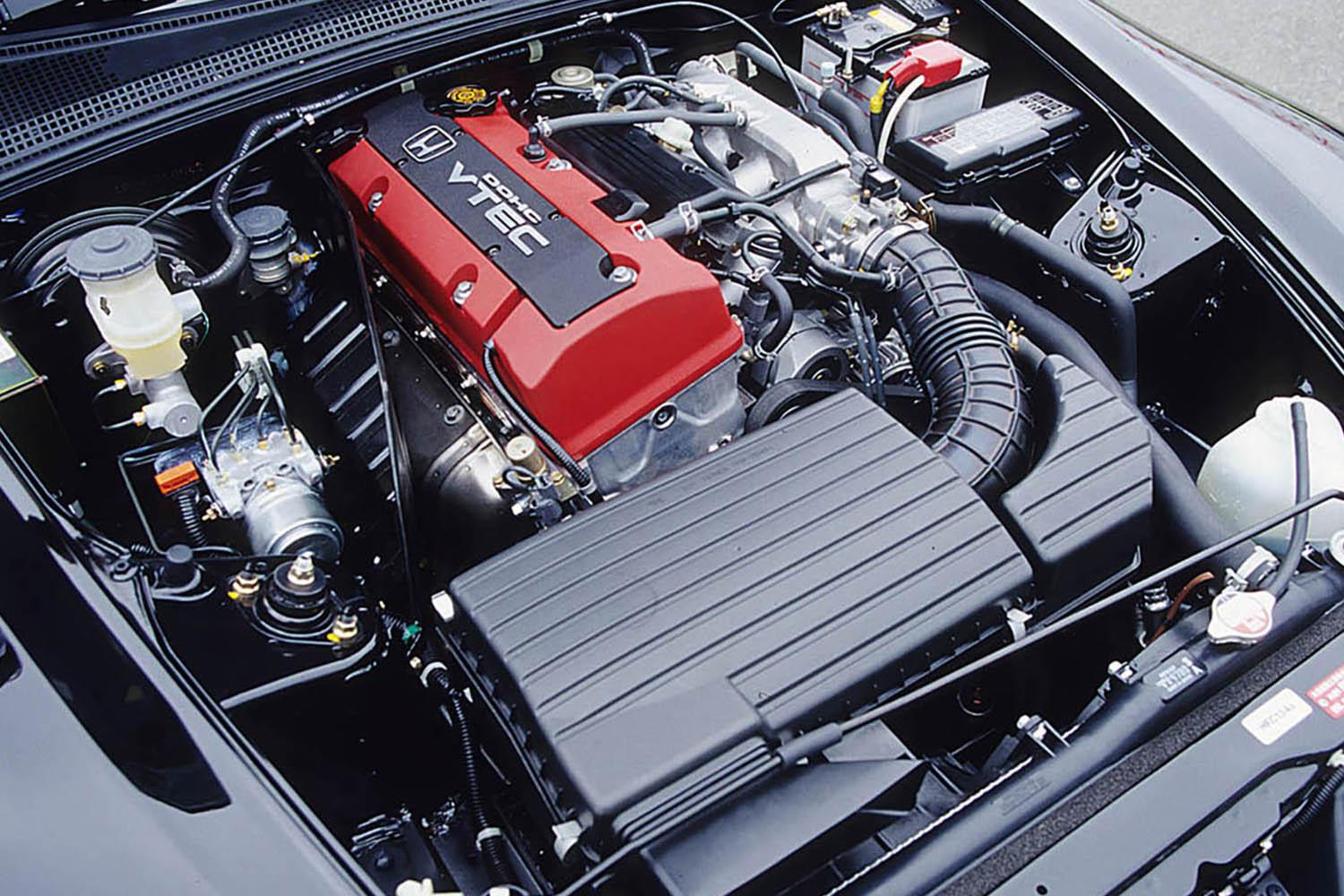 S2000エンジン画像はこちら
S2000エンジン画像はこちら
おどろくべきは最大トルクの発生回数数が7500rpmとなっていること。いまどきのダウンサイジングターボでは1500rpm前後から最大トルクを発生するといったスペックも珍しくないが、S2000のF20Cエンジンは7500rpmから本領発揮という超高回転エンジンなのだ。
 S2000走り画像はこちら
S2000走り画像はこちら
それにしても、これほどの高回転キャラなのだからS2000のエンジンは唯一無二の存在として輝いていた……と思うかもしれないが、2000年代の国産車というのはそんなに甘い世界ではなかった。

